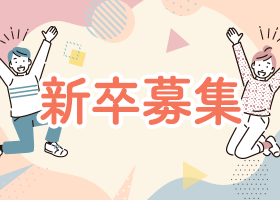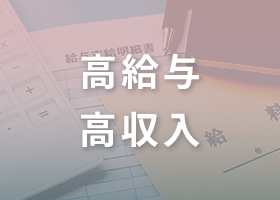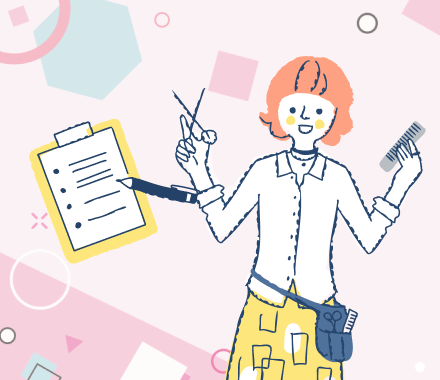将来のキャリアを見据え、転職を考え始めたとき、いまの職場の福利厚生に不安を感じていませんか?社会保険の有無は、日々の安心感はもちろん、将来受け取る年金額にも大きく影響します。万が一の病気やケガ、ライフイベントのことを考えると、その重要性はますます高まるでしょう。
本記事では、美容師が知っておくべき社会保険の基本的な仕組みから、利用できる傷病手当金や産休・育休中の給付制度まで解説します。ご自身の未来を守り、よりよい職場を選ぶための知識としてお役立てください。
美容師の社会保険の現状
美容業界では社会保険への関心が年々高まっています。しかし、その加入率はほかの業界と比べて、まだ高いとはいえないのが実情です。なぜいま、これほど社会保険が注目されているのでしょうか。
ここでは、美容師を取り巻く社会保険の現状について、以下3つの視点から見ていきます。
- 美容業界の社会保険加入率
- いま社会保険が注目される背景
- 社会保険なしで働き続ける将来のリスク
これらの現状を知ることは、ご自身のキャリアプランを考えるうえで大切です。
美容業界の社会保険加入率
美容業界の社会保険加入率は、他業種と比較して低い水準にとどまっています。その理由として、個人経営の小規模サロンが多いことがあげられます。法人化していない個人事業主の美容室では、従業員が何人いても社会保険の加入義務がありません。
また、業務委託契約で働く美容師も増加しており、雇用関係がないため社会保険の対象外となっています。大手チェーン店では社会保険完備のところも増えていますが、業界全体で見ると、まだまだ加入できる環境は限られているのが実情です。このような状況が、美容師の将来への不安につながっているといえます。
参考資料:厚生労働省「個人事業所に係る適用範囲の在り方について」
いま社会保険が注目される背景
近年、美容業界でも社会保険への関心が急速に高まっています。その背景には、深刻な人材不足があります。優秀な人材を確保するため、福利厚生の充実が欠かせなくなってきました。
さらに、2024年10月からは社会保険の適用拡大により、従業員51人以上の企業では週20時間以上働くパート・アルバイトも加入対象です。また、美容師自身の意識も変化しており、技術力だけでなく、安定した労働環境を求める傾向が強まっています。結婚や出産を機に、社会保険完備の職場への転職を考える美容師も増えています。
社会保険なしで働き続ける将来のリスク
社会保険に加入せずに働き続けることには、大きく2つのリスクが伴います。1つ目は、将来受け取る年金額が少なくなることです。国民年金のみの加入となるため、厚生年金に加入した場合と比べて受給額に大きな差が生まれます。
2つ目は、万が一の際の保障が手薄になる点です。たとえば、病気やケガで長期間働けなくなった場合の「傷病手当金」や、出産時に受け取れる「出産手当金」がありません。目先の手取り額は多く感じるかもしれませんが、長期的な視点でこうしたリスクを理解しておくことが大切です。
美容師が知るべき社会保険の基礎知識
社会保険は、私たちの生活を守る制度です。しかし、その内容を詳しく理解している美容師は少ないのではないでしょうか。社会保険に加入することで、どのような保障が受けられるのか、以下5つの項目に分けて解説します。
- そもそも社会保険とは
- 病気やケガに備える健康保険(40歳以上は介護保険料も含む)
- 将来の年金を支える厚生年金保険
- 失業時に受けられる雇用保険
- 仕事中の事故を補償する労災保険
それぞれの保険がどのような場面で役立つのか、具体的に見ていきましょう。
そもそも社会保険とは
社会保険とは、国が運営する公的な保険制度の総称です。会社員が加入する社会保険は、健康保険と厚生年金保険、雇用保険・労災保険の4つから構成されています。これらは相互扶助の精神に基づき、みんなで保険料を出し合って、困った人を助ける仕組みです。
最大の特徴は、保険料を会社と従業員で折半することです。つまり、実際の保険料の半分は会社が負担してくれます。一方、個人事業主やフリーランスの美容師が加入する国民健康保険や国民年金は、全額自己負担となります。この差は、長期的に見ると大きな経済的メリットとなるでしょう。
病気やケガに備える健康保険(40歳以上は介護保険料も含む)
健康保険は、病気やケガで医療機関にかかった際の医療費負担を軽減する制度です。病院の窓口で保険証を提示すれば、医療費の自己負担は原則3割で済みます。また、ひと月の医療費が高額になった場合に、上限額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」も利用できます。
この健康保険は、従業員本人だけでなく、扶養している家族も利用可能です。なお、40歳以上65歳未満の医療保険加入者には介護保険の加入が義務付けられ、健康保険料とあわせて介護保険料も納めることになります。
将来の年金を支える厚生年金保険
厚生年金保険は、老後の生活を支える制度です。国民年金(基礎年金)に上乗せされる形で支給されるため、国民年金のみの加入者と比べて、受給額に大きな差が生まれます。
保険料は給与に応じて決まり、会社が半分負担。障害を負った場合の障害年金や、死亡時の遺族年金も、国民年金より手厚い保障となっています。美容師として長く働き続けるなら、厚生年金への加入は老後の生活設計において極めて重要といえるでしょう。
失業時に受けられる雇用保険
雇用保険は、失業時の生活を支える重要な制度です。自己都合退職の場合でも、一定の条件を満たせば失業手当(基本手当)を受給できます。給付額は退職前6ヶ月の平均賃金に基づいて算定され、その割合は50~80%程度です。支給日数は年齢や勤続年数、離職理由によって異なり、90日から最大で360日まで支給される場合があります。
また、再就職が早期に決まった場合は再就職手当も受け取れるため、転職活動の大きな支えとなります。さらに、育児休業給付金や介護休業給付金など、休業時の所得保障も充実。美容師のキャリアチェンジや、ライフイベントに応じた働き方の変更を考える際、雇用保険は心強い味方となるでしょう。
仕事中の事故を補償する労災保険
労災保険は、業務中や通勤中の事故によるケガや病気を補償する制度です。治療費は全額補償され、自己負担はありません。また、仕事を休んだ場合は、一定の条件で休業補償給付が支給されます。
美容師の仕事は、ハサミやカミソリなどの刃物を扱うため、ケガのリスクが高い職業です。薬剤による皮膚トラブルや、長時間の立ち仕事による腰痛なども、労災の対象となる場合があります。保険料は全額事業主負担のため、従業員の負担はありません。万が一の事故に備えて、労災保険の加入は美容師にとって必須といえるでしょう。
美容師が社会保険で利用できる給付制度
社会保険の大きなメリットは、さまざまな場面で生活を支える給付を受けられる点です。とくに、ライフプランが多様化する美容師にとって、これらの制度はキャリアを継続するうえで心強い味方となるでしょう。
ここでは、社会保険に加入していることで利用できる、5つの給付制度を紹介します。
- 産休育休中に受け取れる出産手当金と育児休業給付金
- 病気やケガで働けないときの傷病手当金
- 退職後の生活を支える雇用保険の失業手当
- 家族の医療費負担を軽減する健康保険の被扶養者制度
- 退職後も同じ保険を使える健康保険の任意継続制度
これらの制度を知っているかどうかは、将来の働き方に大きく影響します。
産休育休中に受け取れる出産手当金と育児休業給付金
出産や育児で仕事を休む期間の収入を支える、2つの給付金があります。まず「出産手当金」は、産休中に給与が支払われない場合に、健康保険から支給されるお金です。収入を気にせず、安心して出産に臨むための制度といえます。
次に「育児休業給付金」は、育児休業中に雇用保険から支給されます。原則として子どもが1歳になるまで受け取ることが可能です。これらの制度があることで、収入面の不安が軽減され、産後の職場復帰がしやすくなります。
病気やケガで働けないときの傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガが原因で仕事を休んだときに、健康保険から支給される給付金です。美容師に多い手荒れや腰痛などが原因で、ドクターストップがかかった場合も対象となり得ます。最長で1年6ヶ月間、給与のおよそ3分の2にあたる額を受け取ることが可能です。
国民健康保険にはない、社会保険の大きなメリットの1つです。働けなくなった際の収入の不安を和らげ、治療に専念できる環境を整えるための制度といえるでしょう。
退職後の生活を支える雇用保険の失業手当
失業手当は、会社を退職し、次の就職先を探している間の生活を支えるために、雇用保険から支給されます。一般的に「失業保険」と呼ばれることが多いです。この給付があることで、焦らずに自分に合った転職先を見つけられます。
ただし、誰でもすぐに受け取れるわけではありません。失業手当を受け取るには、一定期間以上の雇用保険への加入が必要です。また、自己都合での退職か、会社都合での退職かによって、給付が開始される時期や日数が異なります。
家族の医療費負担を軽減する健康保険の被扶養者制度
被扶養者制度は、社会保険に加入している本人(被保険者)だけでなく、その人に扶養されている家族も保険の給付を受けられる仕組みです。配偶者や子どもなどを扶養に入れることで、家族は自分で保険料を納めることなく健康保険に加入できます。
ただし、家族を扶養に入れるには、被保険者によって生計が維持されていることなど、一定の条件を満たす必要があります。この制度は、家計全体の医療費負担を大きく軽減できる点が魅力です。
退職後も同じ保険を使える健康保険の任意継続制度
任意継続制度とは、会社を退職したあとも、希望すれば在職中と同じ健康保険に加入し続けられる仕組みです。退職すると通常は国民健康保険に切り替えますが、扶養家族がいる場合などはこちらの方が有利になることがあります。
この制度を利用するには、退職後に保険者への申し出が必要です。注意点として、在職中は会社が半分負担してくれていた保険料が、退職後は全額自己負担になります。保険料を比較検討したうえで、利用するかどうかを判断するのがよいでしょう。
理美容師などが加入できる健康保険組合

会社の社会保険とは別に、理美容業界で働く人などが加入できる健康保険組合や国民健康保険組合が存在します。たとえば、「全日本理美容健康保険組合」や「東京美容国民健康保険組合」といったものです。
これらの組合のうち、「東京美容国民健康保険組合」は個人事業主や社会保険の強制適用事業所ではないサロンで働く人なども対象としています。一方で、「全日本理美容健康保険組合」はおもに理容業・美容業・その他美容関連業を営む法人が対象であり、フリーランスは加入できません。
なお、この組合はあくまで「健康保険」の制度です。そのため、年金は別途、国民年金に自分で加入する必要があります。働き方によっては有力な選択肢となるため、制度を正しく理解しておくことが重要です。
関連記事:理美容師転職イロハのハ【1】美容師・理容師の職場探しにおすすめ!「求人サイト」を賢く使っちゃおう!
まとめ:美容師で社会保険に加入したい場合はご相談ください
美容師として社会保険に加入することは、将来の安定と安心につながる大切な選択です。社会保険完備の職場への転職を検討されている方は、理美容師専門の転職サービス「beauty mirai agent」にお任せください。
全国3万件以上の求人情報から、年収や休日、職場環境など、あなたの希望条件に合った求人をご紹介します。面接の調整や条件交渉も専門のエージェントが代行するため、スムーズに転職活動を進められます。ぜひ無料会員登録から始めてみてください。